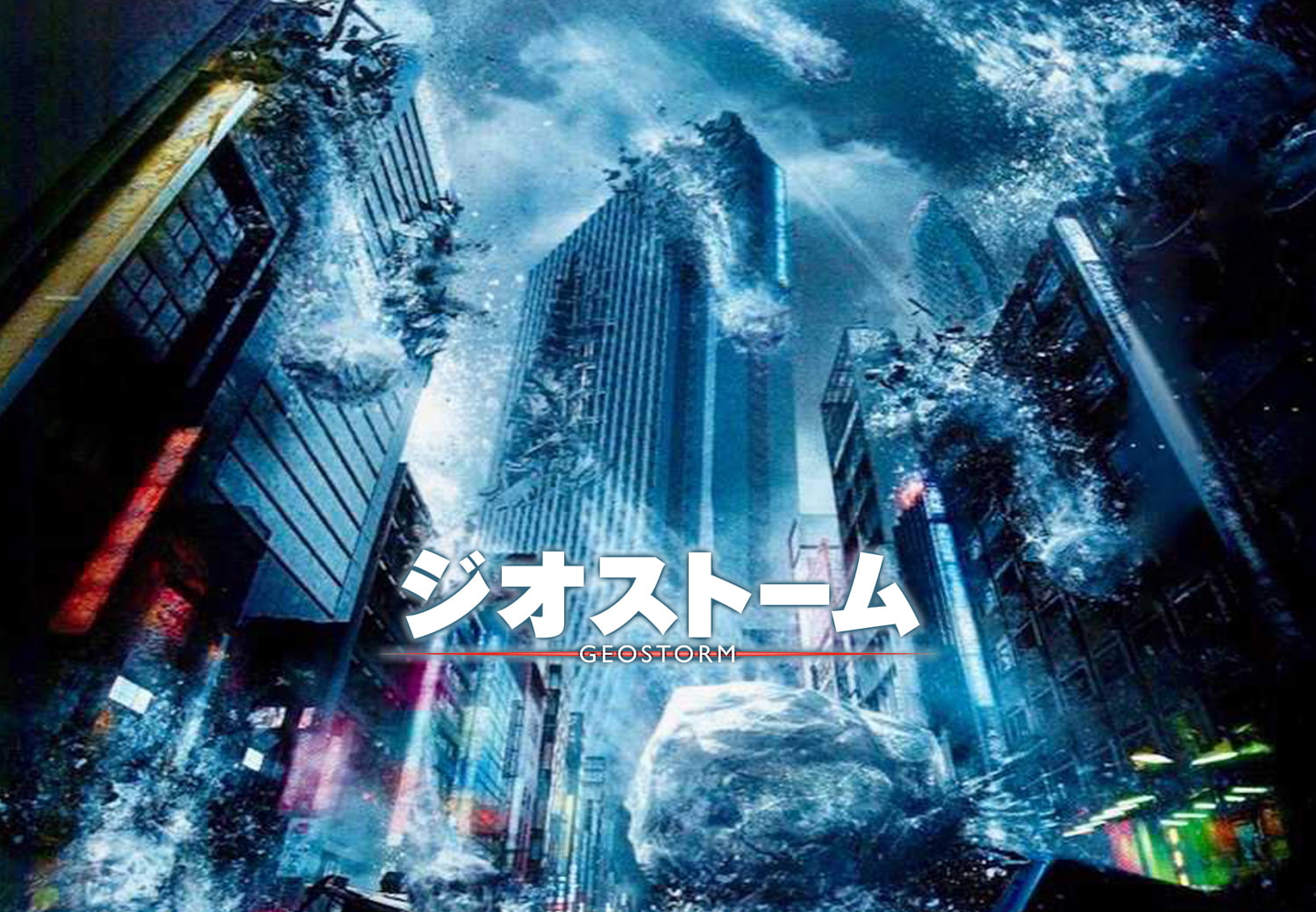「もしも大きな音を発したら、それを聞きつけた”何か”が襲ってくる……」
そんなショッキングな設定で大きな話題を呼んだ「クワイエット・プレイス」は、2018年のホラー映画界を代表する1本と言えます。
予告編でははっきりと描かれない”何か”の正体は「視覚がなく、聴覚が異常に敏感なエイリアン」ということで、内容的にはオーソドックスなモンスターパニックとなっているこの作品。
ホラー映画としての面白さはもちろんですが、一方で「主人公アボット一家の再生の物語」というドラマ面にも大きな魅力があります。
そんな「クワイエット・プレイス」について、掘り下げて評していきましょう。
「音を出してはいけない」世界観の演出センスは抜群
たった一つのルールから生み出される緊張と恐怖
「クワイエット・プレイス」の特徴は、「音を立ててはいけない」というただ一つのシンプルなルールで、これまでのホラー映画とは全く違う斬新な恐怖感と緊張感を生みだした点にあるでしょう。
風や水音といった環境音から外れる音は、通常の話し声レベルでも数百m離れたエイリアンの耳に届き、エイリアンは凄まじい速度で迫ってきて、一瞬で人間を仕留めます。
世界中にそんなエイリアンが蔓延したことで、「歩く」「食べる」「物を動かす」といった生活動作の全てが致命的なミスにつながりかねない危険性をはらみます。
登場人物も観客も、引き金に指をかけた銃を常に頭に突きつけられているかのような緊張感を与えられます。
この緊張感を最大限に活かすための描写の盛り込み方に、主演の一人(父親リー役)でもありこの映画の監督でもある、ジョン・クラシンスキーの抜群の演出センスを感じさせられました。
まず、最初に観客に大きなインパクトを(人によってはトラウマを)与えるのが、冒頭でまだ4歳だったアボット一家の末っ子ビューが、音の出るおもちゃを作動させてしまいエイリアンに殺されるシーンでしょう。
映像的にもショッキングなこのシーンが最初に来ることによって、観ている私たちはこの映画の世界観とルールを一発で頭に叩きこまれます。
そして、これがトリガーとなり、観客はアボット一家のあらゆる動作に「あぁっ危ない気をつけて気をつけて……」と、見ていられないほどのハラハラを感じさせられます。
物を倒したりするミスが起こるたびに、心臓が飛び出すような恐怖を与えられることに。
音を出してはいけないvs声を出さずにはいられない
後半にいくにつれてこのハラハラの頻度も増していきますが、その中でも特に観客の鳥肌のツボを押さえているな、と感心させられるのが「音を立てられない世界で、思わず声を上げずにはいられない描写を盛り込む」ところです。
その代表的なポイントが、階段の途中に突き出していた釘をイヴリンが気づかずに踏み抜くシーンですが、観ているこちらも背中がゾクッとして、思わず口を押えてしまいますよね。
さらに、臨月のイヴリンがエイリアン襲撃の最中に産気づくシーンは、ホラー描写としてはこの映画のクライマックスと言えるでしょう。
お腹の中の赤ちゃんは容赦なく生まれ出ようとしてくるのに、すぐ真後ろには獲物の気配を探すエイリアン。
自分がイヴリンの立場にいることを想像するだけで、嫌な汗が出てきそうですね。
どうしようもない絶望的な状況は、特に出産経験のある女性にとってはトラウマ必至の恐怖シーンではないでしょうか。
どうしても気になるストーリー描写の疑問点も
「もっと上手にサバイバルできたのでは?」という疑問
恐怖シーンのスリルはホラー映画として画期的なレベルですが、アボット一家の日常のサバイバルをはじめとして、どうしても脚本上「作り込みが甘くない?」と思える描写も多くあります。
例えば、終盤では彼らの避難シェルターとして「入り口をベッドで覆った地下室」が登場し、そこでリーとイヴリンは「ここなら大丈夫」と普通に会話をしています。
ですが、観客としては「だったら普段からそこで暮らせよ!」というツッコミをせずにはいられません。
一家団欒中にうっかりガラスランプを倒してあわや一家全滅!となるシーンも、はじめから地下で暮らしていれば起きなかった危機ではないでしょうか(映画的にはハプニングがある方が盛り上がりますが……)。
さらに、リーが息子のマーカスを連れて滝に行き、「ここなら大声をあげても大丈夫」と語るシーンも、同じくツッコミポイントです。
この滝のシーンは、世界中の観客から「そこで暮らせよ!」という声が相次いだそうですね。
エイリアンの強さに納得がいかない
「クワイエット・プレイス」で登場するエイリアンは確かに恐ろしい存在ですが、これが「人類をほとんど滅ぼして文明を崩壊させた」というほどの強敵かというと、疑問がわきます。
確かに生身の人間では到底太刀打ちできない化け物ですが、作中ではイヴリンのショットガンの一撃で絶命するなど、武器さえあれば現実的に戦える存在のようです。
ということは、戦車やヘリといった軍隊レベルの装備があれば、そもそも敵ではないように思えてしまいます。
また、作中ではリーガンの補聴器から発せられる音がエイリアンの動きを止める弱点になっていましたが、こんなシンプルな弱点なら、もっと早く人類に発見されていたのでは?という気もしてしまいます。
「クワイエット・プレイス」にはホラー映画としてのハラハラ要素は豊富にありますが、「一貫して作り込まれたリアルな世界観」があるかと言われると、やや疑問かもしれません。
真の見どころは「主人公一家の再生のドラマ」?
「クワイエット・プレイス」は全編にわたってホラーテイストというわけではなく、静かな世界の中で生きていくアボット一家の人間ドラマ的な要素も強くなっています。
一家4人の中に根深くあるのは、「4歳の息子(弟)を守れなかった」という後悔と自責の念です。
ビューが犠牲になる原因のおもちゃを取り上げなかったリーガンの後悔は特に深く、彼女は「自分が甘さを見せたことで弟は死んだ。だから父親リーは愚かな自分を愛していない」という想像に苦しめられ続けます。
そこから生まれるリーとリーガンのすれ違いの描写は、セリフがほぼないことで簡潔ながら、本格ヒューマンドラマにも引けを取らない心の揺れ動きを繊細に表しています。
「キャスト全員がほぼ表情と短い手話だけで演じる」という異色の作品ですが、全員が本当の家族にしか見えないリアルな息づかいが感じられて、最後の展開には思わずウルっとしてしまいます。
「エイリアンとの戦いとサバイバル」だけでなく、「気持ちがすれ違っていた家族の再生」という物語も、「クワイエット・プレイス」のまぎれもない魅力のひとつです。
最後に
パニック映画としてのルール付けや世界観の書き込みに難点は感じられるものの、後半45分の怒涛の戦いやまさかの感涙ヒューマンドラマ描写など、エンタメ映画としての見どころが満載の「クワイエット・プレイス」。
寿命を削るようなサバイバル描写とキャストの名演が光るストーリーは、「異色設定の斬新なホラー」というキワモノ感を抜きにしても一見の価値ありと言えるでしょう。
大ヒットを受けて続編の製作も進んでいるそうですが、アクションテイストになることを匂わせて終わったこの映画がどんなふうに発展していくのか、今から期待が高まりますね。