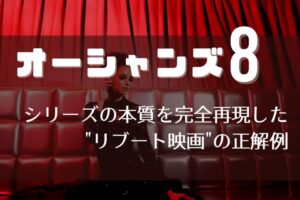2011年に発生した「ノルウェー連続テロ事件」。
単独犯の男が首都オスロで爆破テロを起こし、その直後に付近の島のキャンプ施設に上陸、数十人の少年少女を殺害したこのおぞましい事件は、今も記憶に残っている方も多いのではないでしょうか。
個人の一度の犯行としては歴史上最多の犠牲者を出したこの事件を映画化したのが、Netflixオリジナル作品として配信されている「7月22日」です。
あまりにも恐ろしく救いがないこの事件を、関係者の目線で生々しく描いたこの作品。
その内容を、掘り下げていきましょう。
淡々としているからこそ背筋が凍るテロ描写
テロ事件のその後の展開と、被害者の少年の立ち直りをメインに描く「7月22日」では、実際のテロ描写は映画の序盤のうちに終わります。
「爆発」「銃撃」といった激しい犯行がくり広げられたこの事件ですが、映画ではアクション的な要素は排して、犯人の行動が淡々と描かれます。
ですが、このように「地味」な犯行シーンが展開されるからこそ、その現実的な恐ろしさがよりダイレクトに伝わってくるのが印象的です。
これがアクション映画なら、数で勝る少年少女たちは犯人に抵抗する意志を見せるのかもしれません。
ですが、現実ではごく普通の高校生たちにそんなことができるはずもなく、彼らは「銃」という一方的な武器の前に、ろくに逃ることもできずに死んでいきます。
描写が淡々としているからこそ「これは現実に起きたことで、逃げる術も逆転するチャンスもなかったんだ」と思えて背筋が凍る、戦慄のテロシーンです。
生々しく描かれるトラウマと悲壮感
犯人ブレイビク(アンデルシュ・ダニエルセン・リー)に何発も銃撃されて、瀕死になりながらも生き残った主人公の少年ビリヤル(ジョナス・ストランド・グラヴリ)。
ですが、ことは「生き残った、よかった」という単純な話ではなく、その後の彼の苦しみは、見ていて息が詰まるようでした。
まず、「目の前で親友たちが撃ち殺され、自分も執拗に体中を撃たれて死にかけた」という経験が、ごく普通の10代の少年にトラウマを残さないはずがありません。
大人の私たちでも、こんな経験をしてしまったら心が壊れてしまうかもしれませんよね。
さらに、「右目や手の指を失い、歩くことすらリハビリを必要とし、頭に残った銃弾の破片を取り除くまではいつ死んでもおかしくない」という怪我の爪痕も、ビリヤルの精神をえぐります。
ある日突然、こんな理不尽な暴力と殺意にさらされて、その後の人生にも一生残る傷跡を負わされる。
その苦しさは、第三者の私たちではとても想像しきれません。
そんなビリヤルが映画の中盤にわたって見せる葛藤や不安感は、主演ジョナス・ストランド・グラヴリの抑えた演技によって、生々しく観客に伝わってきます。
証言シーンで主人公が見せた唯一の「勝利」
爆破事件も含めると77人が亡くなり、生存者もトラウマや後遺症、社会の目や心ない誹謗中傷に悩まされ、さらに死刑制度のないノルウェーでは今もブレイビクが生き続けているなど、どこまでも救いのないこの事件。
ですが、映画後半の裁判シーンでビリヤルが見せた証言は、この事件におけるほぼ唯一の「勝利」と言ってもいいものでした。
裁判で犯人と対峙する覚悟を決めたビリヤルが、証言の場で被告ブレイビクをまっすぐ見据えながら語るシーンは、この映画が伝える一番のメッセージを含んでいます。
『僕にはまだ、家族がいる。友達も、思い出も、夢も、希望も、愛も。でもこいつは孤独で、何一つ持ってない。きっと刑務所で朽ち果てるだろう。僕は生き延びた。これからも生きる』
(引用:https://www.netflix.com)
ビリヤルに真正面からこの言葉を浴びせられたとき、ブレイビクはビリヤルから目を逸らし、うつむいてしまいます。
多くの傷跡を残されても、最後にはくじけることなく、堂々と「これからも生きる」と犯人の目の前で宣言したビリヤル。
彼はこの証言で、「犯人に屈しなかった」という意味で勝利したと言えるのではないでしょうか。
それまでのビリヤルの苦悩を観ているからこそ、このシーンでは感動や安心、小気味よさすら感じられます。
犯人ブレイビクに垣間見える「幼稚さ」と「寂しさ」
被害者や関係者の内面をリアルに描いている「7月22日」ですが、取り調べや裁判のシーンを通して、あまり知られていなかった犯人ブレイビクの人間性が垣間見える点も注目ポイントです。
これだけの事件を起こして「自分は正義の行いをした」と言い切り、収監されてからも「独房の娯楽品がつまらない」という苦情を公表するなど、世間一般では「サイコで得体の知れない殺人鬼」というイメージの強いブレイビク。
ですが、この映画を観ると、彼の幼稚さや寂しがりな一面がうかがえて、「こいつは得体の知れない化け物なんかじゃなく、ただの臆病な男だった」と思えます。
例えば、取り調べで「同じ思想の同志が自分に続くだろう」とブレイビクが執拗に語るシーン。
この言動は裏を返せば「誰かが自分に続いてほしい、自分は独りじゃないと証明してほしい」という気持ちが透けて見えます。
さらに彼は、証言者として裁判に招致された極右活動家に「この男の暴力は何の後押しにもならない」と言われたときは子どもじみた憤りを見せ、刑務所に入るときに担当弁護士に「もう面会には来ない」と言われると素直に寂しそうな表情を見せます。
極めつけは、ビリヤルに「こいつは孤独で、何一つ持ってない」と言われたときの、図星をつかれたうつむき顔です。
銃を持って襲いかかった相手に、最後には自分の孤独さと無力さを突きつけられる。
そんなブレイビクは「ただの暴走した一人の男」であって、彼一人にノルウェーや世界が敗北することなんてあり得ないと信じられます。
一部の過激派から「英雄」として持ち上げられ、世間から「化け物」として恐れられたブレイビクの化けの皮を剥いだ、という点でも、「7月22日」は重要な映画ではないでしょうか。
最後に
重苦しい題材を描いた「7月22日」ですが、決して最後まで救いがないわけではなく、精神的な意味での「希望」「勝利」も見えて、後味のいい結末を迎えます。
また、ノンフィクション映画だからといって堅苦しい仕上がりになっているわけではなく、ちゃんとヒューマンドラマとして「面白い」と言える作品になっています。
現実に起きた悲劇をより深く知れる、という点でも、トラウマを乗り越えて生きていく青年のドラマに感動できる、という点でも、一度は観る価値のある名作です。